第1章:はじめに|なぜキャリア迷子になるのか?

「今の仕事、このままでいいのかな?」
そう感じたことはありませんか?
努力してきたはずなのに、なぜか心が満たされない。
やりたいこともわからない。
気づけば周囲のSNS投稿と自分を比べて、焦りや不安が募る――。
そんな「キャリア迷子」状態に陥る人が、今とても増えています。
その背景には、時代の変化があります。
転職が当たり前になり、働き方の選択肢も増えた一方で、「何を基準に選べばいいのか」が見えにくくなったのです。
SNSでは他人の成功や華やかなキャリアが溢れ、知らず知らずのうちに“他人軸”で自分を評価してしまう。
結果、「自分はどう生きたいのか」が見えなくなり、迷いが深まります。
けれど、安心してください。
迷うことは、決して悪いことではありません。
それは、あなたが“自分らしく生きたい”と心の奥で感じている証拠です。
むしろ「迷い」は、成長のサイン。これまでの延長ではなく、「本当の自分に合った道」を探し始めた合図なのです。
では、どうすればこの迷いを“自分の軸”に変えられるのでしょうか?
その答えが、「自己分析」です。
この記事では、過去の経験を棚卸しし、自分の価値観や強みを見つけ、未来のキャリアを設計する8つのステップを紹介します。
キャリアに迷う時間を、「自分を深く知る時間」に変えていきましょう。
あなたが“迷わない自分”になるための第一歩は、ここから始まります。
第2章:キャリア迷子が陥る3つの罠

キャリアに迷ってしまう人には、実は共通のパターンがあります。
それは、自分の価値観や目標よりも「他人軸」「過去軸」「理想軸」に縛られてしまうことです。
ここからは、迷いを生む3つの典型的な罠を具体的に見ていきましょう。
1.【他人軸】まわりの評価や常識に流されてしまう
キャリア迷子になる大きな原因のひとつが、「他人軸」で生きてしまうことです。
他人の評価や世間の常識に合わせて選択すると、本来の自分の価値観や興味が置き去りになるからです。
その結果、どれだけ成果を出しても心が満たされず、「自分は何をしたいのだろう」と迷いが生まれます。
例えば、「安定しているから」という理由で大企業に就職したものの、やりがいを感じられず転職を繰り返す人がいます。
外から見える“正解”を選び続けた結果、自分の内側の声を無視してきた典型です。
他人軸を手放し、「自分が何を大切にしたいのか」を基準に選ぶことこそが、迷わないキャリアの第一歩です。
2.【過去軸】一度の成功体験にしがみつく
キャリアが行き詰まる原因のひとつに、「過去の成功体験にしがみつく」ことがあります。
かつてうまくいった方法や評価された経験に固執すると、環境や自分の価値観が変わっても同じやり方を続けてしまいます。
その結果、成長の機会を逃し、新しい挑戦に踏み出せなくなるのです。
例えば、営業職で「努力と根性」で成果を上げた人が、その経験を手放せず、変化の速い市場で苦しむケースがあります。
以前の成功は過去の自分に合ったものであり、今の自分に最適とは限りません。
キャリアを進化させるためには、過去の栄光を“誇り”として残しつつも、“基準”にしない勇気が必要です。
過去を手放すことで、新しい可能性が見えてきます。
3.【理想軸】「やりたいこと」を完璧に見つけようとして動けなくなる
「本当にやりたいことを見つけなきゃ」と焦るあまり、かえって動けなくなる人が多くいます。
多くの人は“たったひとつの正解”を探そうとしますが、やりたいことは最初から明確にあるものではなく、行動の中で少しずつ形になるものだからです。
完璧な答えを探そうとするほど、現実とのギャップに苦しみ、時間だけが過ぎてしまいます。
「自分の使命を見つけたい」と悩み続けて転職や副業を始められない人がいますが、実際に動いてみることでしか、本当に心が動く瞬間は見つかりません。
理想を追いすぎず、まず小さく行動してみること。
完璧なやりたいことより、「今やってみたいこと」から始めることが、キャリア迷子を抜け出す第一歩です。
4.「迷いの正体」を言語化し、次章の“自己分析”へ自然に誘導する
キャリアの迷いを解消する第一歩は、「なぜ迷っているのか」を言葉にすることです。
多くの人は、漠然とした不安を抱えたまま動けなくなっています。
けれど、その“もやもや”の正体を言語化できれば、問題の原因が見え、次に何をすればいいかが明確になります。
例えば「今の仕事が合わない」と感じている場合でも、本当の原因は“成長できていない不満”なのか、“人間関係のストレス”なのかで、取るべき行動はまったく違います。
つまり、迷いを言語化することは、自分の内側を整理する「自己分析」の第一歩。
次章では、その具体的な方法を通して、あなた自身の軸を見つけていきましょう。
第3章:自己分析がキャリア迷子を救う理由

迷いの正体が見えてきたら、次は具体的に自分を理解するステップです。
自己分析は単なる作業ではなく、自分の価値観や強みを言語化し、判断の軸を持つための手段。
ここからは、なぜ自己分析がキャリア迷子を救うのか、その理由を詳しく見ていきましょう。
1.自己分析=「自分という資産の棚卸し」
自己分析とは、自分の経験やスキル、価値観を整理する「自分という資産の棚卸し」です。
自分の強みや得意分野、興味・価値観を言語化することで、選択の軸が明確になり、迷わず意思決定できるようになります。
逆に棚卸しをせずに動くと、他人の評価や流行に振り回されやすくなります。
例えば、過去の経験を振り返り「チームをまとめるのが得意」「新しいアイデアを形にするのが好き」と整理するだけで、自分に向いている職種や働き方のヒントが見えてきます。
自己分析=資産の棚卸しは、キャリア迷子を抜け出し、自分らしい道を描くための第一歩です。
まずは自分の過去や経験を丁寧に書き出してみましょう。
2.外部環境(転職市場・流行)ではなく、自分の内側に軸を持つ重要性
キャリア選択で迷わないためには、転職市場や流行などの外部環境に振り回されず、自分の内側に軸を持つことが重要です。
外部の情報は常に変化します。
流行や他人の成功に従って判断すると、一時的には正解に見えても、長期的には満足感や成長を得られないことが多いのです。
自分の価値観や強みを基準にすると、変化に左右されず安定した意思決定が可能になります。
例えば、周囲がこぞって人気業界に転職しているからといって飛びつくと、自分に合わずストレスを抱えるケースがあります。
一方、自分の軸(「挑戦」「自由」「成長」など)を明確にしていれば、流行に左右されず納得感のある選択ができます。
外部環境に惑わされず、自分の内側に軸を置くことが、迷わないキャリアを築く鍵です。
まずは自分の価値観と強みを言語化して、判断基準を持ちましょう。
3.自己理解が深まると「選択に迷わなくなる」心理的根拠
自己理解を深めることで、キャリアの選択に迷いが生じにくくなります。
人は判断の基準が不明確なとき、他人の意見や社会の常識に依存しやすくなります。
自己理解が進むと、自分の価値観や強み、興味が明確になり、意思決定の際の「判断軸」がはっきりします。
その結果、外部の情報に振り回されず、自信を持って選択できる心理状態が作られます。
例えば、「自由な働き方」を重視する人が自己分析で自分の強みや価値観を理解すると、転職やプロジェクト選択の際に「自由度が高いかどうか」という明確な基準で判断できます。
迷いが減り、選択に対する納得感と満足感も高まります。
つまり、自己理解は単なる自己満足ではなく、迷わないキャリア選択を支える心理的な土台です。
迷ったときこそ、自分の軸を確認する習慣が重要です。
第4章:過去を棚卸しして、自分の原点を知る
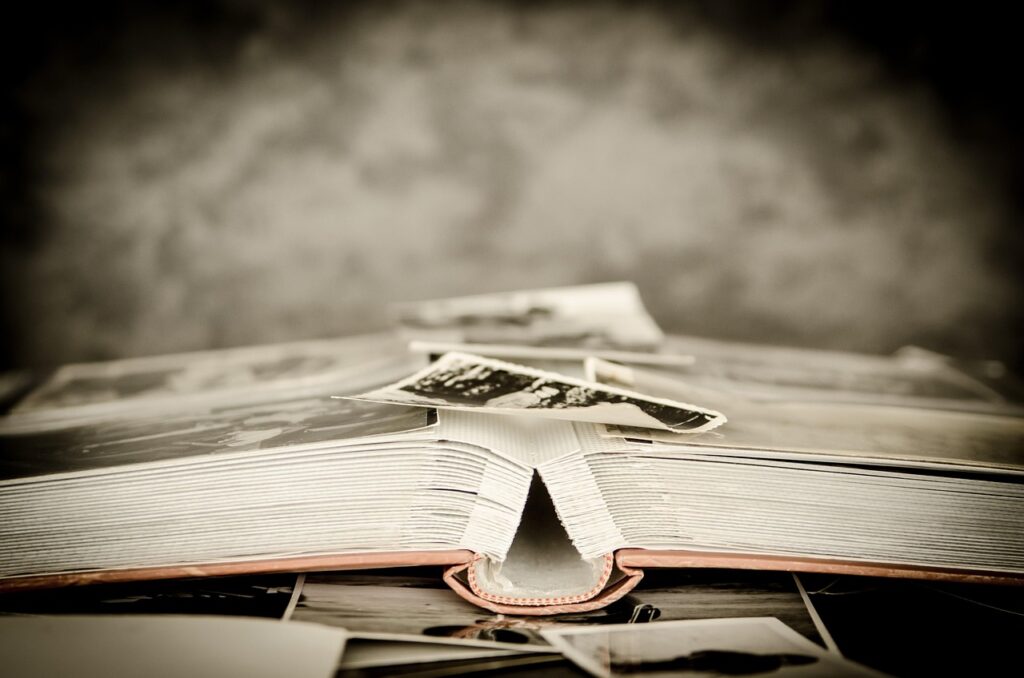
キャリア迷子を脱するための第一歩は、まず自分の過去を丁寧に振り返ることです。
過去の経験には、あなたの価値観や強み、心が動いた瞬間のヒントが隠されています。
小さな成功体験や失敗の中にも、自分らしさを知るための重要なサインがあります。
この章では、過去の出来事を棚卸しし、自分の原点を言語化する方法を具体的に紹介します。
1.学生時代~現在までの「印象に残った出来事」を時系列で振り返る
自己分析の第一歩は、学生時代から現在までの印象に残った出来事を時系列で振り返ることです。
出来事を時系列で整理することで、成功や失敗、嬉しかった経験や挫折などを客観的に俯瞰でき、自分の価値観や行動パターンの一貫性に気づきやすくなるからです。
これにより、自分の原点や強みが明確になり、今後の選択の基準を作ることができます。
例えば、学生時代に部活動でキャプテンを務めた経験、大学でのゼミ活動、初めてのアルバイトでの成功体験などを時系列で書き出すと、「人をまとめるのが得意」「計画を立てて実行することに喜びを感じる」といった自分の特徴が見えてきます。
過去を整理することは、自己理解を深める重要なステップです。
印象に残った出来事を書き出し、自分の行動や感情のパターンを見つけることから始めましょう。
2.「夢中になったこと」「得意だったこと」「他人に褒められたこと」を抽出する
自己分析では、自分が夢中になったこと、得意だったこと、他人に褒められたことを整理して抽出することが重要です。
これらの要素は、あなたの強みや価値観を示す重要な手がかりだからです。
夢中になったことはモチベーションの源泉、得意なことは再現性のある成果、他人から褒められたことは客観的な強みとして活かせます。
これらを明確にすることで、自分らしいキャリアの方向性を描きやすくなります。
例えば、学生時代に部活動で企画を立てるのが楽しく、アルバイトで接客を褒められ、趣味ではブログを書いていた場合、「計画力」「コミュニケーション力」「文章力」が自分の強みとして見えてきます。
抽出作業を通じて、自分が何に価値を感じ、どの分野で力を発揮できるかが明確になります。
自己分析の基盤として、これらを丁寧に書き出すことから始めましょう。
3.「なぜそれが楽しかったのか?」を掘り下げて価値観を見出す
自己分析では、過去の経験が「なぜ楽しかったのか」を深掘りすることで、自分の価値観を明確にできます。
出来事そのものではなく、その背後にある感情や理由に注目することで、自分が本当に大切にしていることが見えてくるからです。
価値観は意思決定の軸となるため、キャリア選択の基準を作るうえで不可欠です。
例えば、学生時代に部活動で大会に向けて仲間と練習を重ねるのが楽しかった場合、「勝利そのもの」ではなく「チームで協力して目標を達成する過程」に喜びを感じていたことに気づきます。
これにより、自分の価値観は「協働」と「達成感」にあると整理できます。
過去の体験をただ振り返るだけでなく、「なぜ楽しかったのか」を掘り下げることで、自己理解が深まり、迷わないキャリアを築くための確固たる軸を見つけることができます。
4.シンプルなワークシート例を紹介する
自己分析を効率的に行うには、シンプルなワークシートを使って過去の経験や価値観を整理する方法がおすすめです。
頭の中だけで振り返ると抜けや偏りが出やすく、何を大切にしているのかも曖昧になりがちだからです。
ワークシートを使うことで、経験・感情・学び・価値観を可視化し、体系的に整理できます。
例えば、横軸に「学生時代」「社会人」「現在」、縦軸に「夢中になったこと」「得意だったこと」「他人に褒められたこと」「学び・気づき」を書き込み、出来事を埋めていきます。
さらに「なぜ楽しかったのか」を問いとして追記することで、自分の価値観や強みが自然と浮かび上がります。
このようなシンプルなワークシートは、自己分析を効率的かつ具体的に進めるための強力なツールです。
まずは紙でもデジタルでも良いので、手を動かして書き出してみましょう。
第5章:価値観マップを作り、自分の“軸”を言語化する
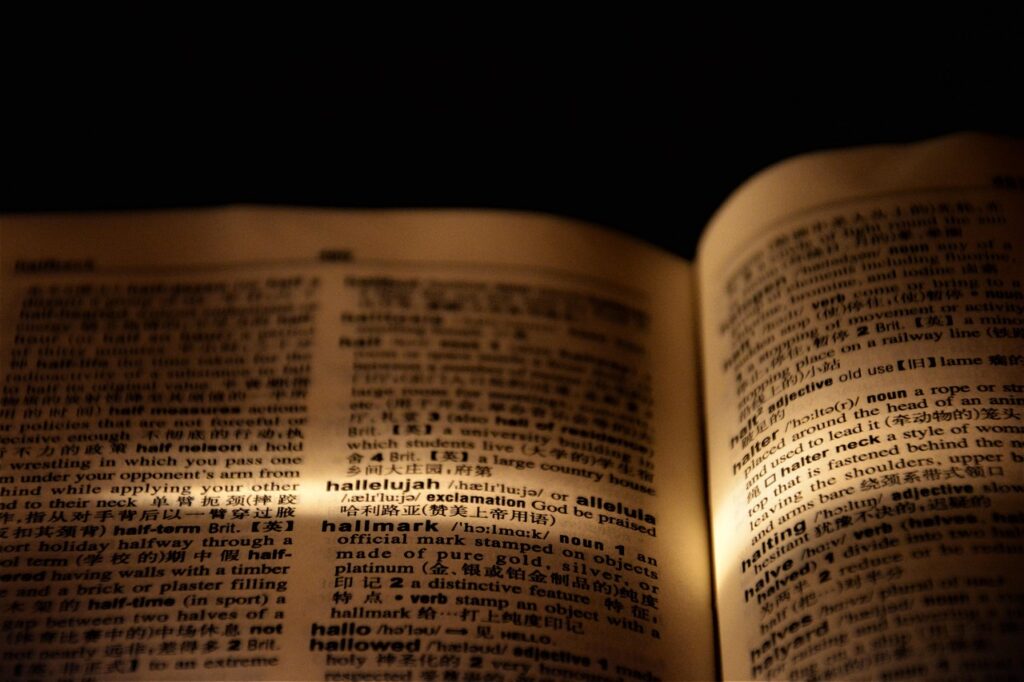
自己分析で過去の経験や強みを整理できたら、次は自分の価値観を可視化するステップです。
価値観を明確にすることで、「何を大切にして生きたいのか」「どのような働き方が自分に合うのか」が判断しやすくなります。
この章では、価値観マップを使って、自分の軸を言語化し、迷わない意思決定につなげる方法を具体的に紹介します。
1.価値観リスト例:「挑戦」「安定」「自由」「貢献」「成長」「仲間」など
キャリア選択の軸を明確にするには、まず自分の価値観をリスト化して整理することが有効です。
価値観は、仕事や人生で何を重視するかを示す判断基準だからです。
明確な価値観を持つことで、選択や意思決定の際に迷いが減り、自分にとって最適な道を見つけやすくなります。
例えば「挑戦」を重視する人は新しいプロジェクトや変化の多い環境にやりがいを感じ、「安定」を重視する人は長期的な収入や職場環境の安定性を大切にします。
「自由」「貢献」「成長」「仲間」といった価値観も同様に、自分の意思決定の軸として活用できます。
まずは価値観リストを参考に、自分にとって重要なものをピックアップし、優先順位をつけることが、迷わないキャリアを築く第一歩です。
2.トップ3を選び、それぞれの背景にあるエピソードとの紐づけ
自己分析では、自分の価値観の中から特に重要なトップ3を選び、それぞれに具体的なエピソードを紐づけることが大切です。
抽象的な価値観だけでは、意思決定の軸として活かしにくく、迷いの原因になります。
エピソードと結びつけることで、なぜその価値観が大切なのかが明確になり、判断や行動に具体性が生まれます。
例えば「挑戦」をトップ1に選んだ場合、大学で新規イベントの企画を任された経験や、初めての仕事で難題に取り組んだ成功体験を紐づけます。
「仲間」を選んだ場合は、チームで協力して成果を出した経験などを書き出すと、自分の軸が具体的に理解できます。
価値観トップ3をエピソードと結びつけると、自分の意思決定の基準が明確になり、迷わず選択できるキャリアの軸を作れます。
3.「私が大切にしたい生き方=キャリアの軸」を明文化する方法
キャリア迷子を脱するには、自分が大切にしたい生き方を言語化し、それを「キャリアの軸」として明確にすることが重要です。
頭の中で漠然と考えているだけでは、選択の際に迷いやすくなります。
言語化することで、自分の価値観や優先順位が明確になり、判断基準として日常の意思決定に活用できるからです。
例えば、「挑戦」「成長」「仲間」を軸に選んだ場合、「新しいことに挑戦できる環境で、成長を実感しながら、チームで協力して成果を出す」という一文にまとめると、自分のキャリア選択や転職判断の基準として明確に使えます。
価値観と経験を整理したうえで、具体的な言葉に置き換えると、「自分の軸」を日々の意思決定に活かせます。
まずは一文でも良いので、キャリアの軸を明文化してみましょう。
第6章:強みを“行動の癖”から見つける

過去の経験や価値観を整理して自分の軸を明確にできたら、次は「自分の強み」を具体的に見つけるステップです。
強みとは、単なるスキルではなく、無意識に繰り返している行動パターンや習慣の中に隠れています。
どのような状況で成果を出しやすいのか、どんな場面で周囲に喜ばれるのかを振り返ると、自分の再現性のある強みを発見できます。
この章では、行動の癖から強みを特定する方法やツールを紹介し、自分らしいキャリア選択につなげる方法を解説します。
1.ストレングスファインダーや16Personalitiesなどのツールを活用する
自己分析を深めるためには、ストレングスファインダーや16Personalitiesなどの診断ツールを活用するのが有効です。
これらのツールは、自分ひとりでは気づきにくい強みや思考傾向、行動パターンを客観的に可視化してくれます。
客観データと自身の経験を組み合わせることで、強みや価値観の精度が高まり、キャリア選択に活かしやすくなります。
例えば、ストレングスファインダーで「調整力」「学習欲」「着想力」と出た場合、チーム内での調整役や新しいアイデアの発案に強みがあることが分かります。
16Personalitiesで「ENTJ」と診断されれば、リーダーシップや目標達成志向が高いことも理解できます。
診断ツールはあくまで補助ですが、自分の強みや傾向を言語化する強力な手段です。
結果を踏まえて、自分の行動パターンと照らし合わせると、より具体的なキャリア戦略を描けるようになります。
2.他者フィードバックを活かして“自分では気づけない強み”を見つける
自分では気づきにくい強みを見つけるためには、他者からのフィードバックを積極的に活用することが重要です。
自分では当たり前に感じる行動や能力は、意外と他人から高く評価されることがあります。
他者の視点を取り入れることで、自分だけでは見えなかった強みや行動パターンを客観的に把握でき、自己分析の精度が格段に上がります。
例えば、上司や同僚から「人の意見をまとめるのがうまい」「複雑な課題でも冷静に解決策を提案できる」と言われることがあります。
自分では普通のことだと思っていた行動も、立派な強みとしてキャリアに活かせる要素です。
自己理解を深めるには、自分の内側だけでなく外部の視点も取り入れることが不可欠です。
フィードバックを整理し、自分の強みとして明文化することで、より迷わないキャリア選択が可能になります。
3.「成果の裏には必ず強みの再現パターンがある」ことを説明する
仕事やプロジェクトで出した成果には、必ず自分の強みが繰り返し活かされるパターンがあります。
成果は単なる偶然ではなく、自分の得意な行動や思考の癖が影響しているからです。
強みは無意識に繰り返されるため、過去の成功体験を振り返ることで、どの状況で自分が最大限力を発揮できるかが見えてきます。
例えば、チームでプロジェクトを成功させた経験があった場合、「計画を立てて進捗を管理する」「メンバーの意見を調整する」という行動が繰り返されていることが多いです。
これらが自分の強みの再現パターンであり、今後も活かせる行動指針になります。
過去の成果を分析して行動パターンを見つけることで、自分の強みを明確化できます。
再現パターンを理解することは、迷わないキャリア選択の土台を作る上で不可欠です。
4.強み×価値観=理想の仕事の方向性を見つける
理想のキャリアを描くには、自分の強みと価値観を掛け合わせて考えることが重要です。
強みだけでは「何ができるか」しか見えず、価値観だけでは「何を大切にしたいか」しかわからないからです。
この二つを組み合わせることで、自分が能力を最大限発揮でき、かつ満足感を得られる仕事の方向性が明確になります。
例えば、強みが「人をまとめる力」、価値観が「成長」と「仲間」であれば、チームリーダーやプロジェクトマネージャーのように、人を導きながら成果を出し、メンバーと成長を共有できる仕事が理想的な方向性となります。
強みと価値観を掛け合わせて考えることで、自分に合った働き方や職種が見えてきます。
このプロセスは、迷わないキャリア設計の核心と言えるでしょう。
第7章:3つの視点でキャリアの方向性を描く

自己分析で価値観や強みを明確にできたら、次はそれをもとに具体的なキャリアの方向性を描く段階です。
ただし、一つの視点だけで考えると偏りや迷いが生じやすくなります。
そこで、この章では「過去の経験」「自分の強み」「価値観」の3つの視点からキャリアを立体的に整理し、理想の働き方や職種を見つける方法を解説します。
複数の視点で考えると、自分らしいキャリアをより現実的かつ納得感のある形で描けるようになります。
1.【できること】スキル・得意分野
キャリアの方向性を描く上で、まず自分が「できること」を明確にすることが重要です。
できること、つまりスキルや得意分野を把握することで、どの仕事で自分の力を最大限発揮できるかが分かります。
逆に、曖昧なまま進むと、自分の能力に合わない役割を選んでしまい、ストレスや成果の低下につながります。
例えば、文章作成や企画立案が得意な場合は、コンテンツ制作やマーケティング、プロジェクト企画の仕事が向いている可能性があります。
さらに、過去の成功体験や周囲から褒められた点を振り返ることで、自分の強みが再現性のあるスキルとして確認できます。
「できること」を整理することは、キャリア選択の土台作りです。
自分のスキルや得意分野を言語化し、次のステップである「価値観や強みとの掛け合わせ」に活かしましょう。
2.【やりたいこと】モチベーション・興味
キャリアの方向性を描く上で、自分が「やりたいこと」、つまりモチベーションや興味を明確にすることは不可欠です。
どれだけスキルや得意分野があっても、やりたいことと一致しなければ長期的な満足感や成果は得られません。
やりたいことを把握することで、情熱を注げる仕事や、努力が苦にならない分野を選択できるため、キャリアの成功と幸福感が高まります。
例えば、文章を書くことに興味があり、人に伝えることに喜びを感じる場合、ライティングや広報、マーケティングなどの分野が自然に候補となります。
過去の経験で夢中になったことや達成感を感じた瞬間を振り返ると、自分のモチベーションの源泉が見えてきます。
「やりたいこと」を言語化することは、自分らしいキャリアの方向性を描く重要なステップです。
スキルと組み合わせることで、迷わず進める軸が作れます。
3.【求められること】社会的需要・市場価値
キャリアの方向性を描く上で、「求められること」、つまり社会的需要や市場価値を意識することは重要です。
自分のスキルややりたいことだけに偏ると、需要が少ない分野で苦戦する可能性があります。
市場や社会のニーズを理解することで、能力を最大限活かせる場を見つけやすくなり、キャリアの実現性と安定性が高まります。
例えば、プログラミングスキルがありITに興味があっても、需要が低い特定の古い技術に特化している場合、活躍の場は限られます。
一方、AIやクラウド技術など市場価値の高い分野に自分の強みを合わせると、成長の機会と仕事の満足度が両立しやすくなります。
「求められること」を意識することは、自己理解だけでは見えない現実的なキャリアの可能性を広げる鍵です。
強みと価値観を組み合わせることで、迷わないキャリアの方向性を描くことができます。
4.3つの交点を探す「キャリアトライアングル」を提示
迷わないキャリアを描くためには、「できること」「やりたいこと」「求められること」の交点を見つける『キャリアトライアングル』を活用するのが有効です。
3つの視点を組み合わせることで、自分の強みが最大限活かせる分野、情熱を注げる仕事、そして市場価値が高い領域を同時に確認できます。
この交点こそが、理想的かつ現実的なキャリアの方向性を示す指針になります。
例えば、文章作成が得意(できること)、ライティングが好き(やりたいこと)、コンテンツマーケティングの需要が高い(求められること)場合、この交点にある「コンテンツマーケター」という職種が、自分にとって最適なキャリア方向となります。
キャリアトライアングルを使って交点を明確にすることで、迷いを減らし、強み・価値観・市場ニーズを活かした自分らしい働き方を見つけることができます。
5.実例を交えながら“自分らしい働き方”を描く方法を解説
自分らしい働き方を描くには、自己分析で明確になった「強み」「価値観」「市場ニーズ」を統合し、具体的な職務や環境に落とし込むことが重要です。
抽象的な理想だけでは行動に移せず、現実とのギャップに悩みやすくなります。
過去の成功体験や自分のモチベーションの源泉、社会的需要を組み合わせて描くことで、納得感のある現実的なキャリアプランが見えてきます。
例えば、以下のケースが考えられます。
実例1:クリエイティブ職志向
- 強み:アイデアを形にする企画力
- 価値観:自由に表現できる環境
- 求められること:デザイン・広告業界のクリエイティブ人材
- 具体例:フリーランスとして広告やWebコンテンツの企画・デザインを手がけることで、自分の創造性を最大限活かしつつ、報酬も得られる働き方を実現
実例2:教育・人材育成志向
- 強み:人の成長を支援する能力
- 価値観:貢献・成長の実感
- 求められること:研修やコーチング市場の需要
- 具体例:社内研修担当やキャリアコーチとして働くことで、学ぶ人の成長を間近で支援し、自分も学びながらキャリアを築く
実例3:分析・数値管理志向
- 強み:データ分析・問題解決能力
- 価値観:成果を見える化すること
- 求められること:データサイエンスやマーケティング分野の需要
- 具体例:データ分析担当として売上改善プロジェクトに参画し、数値で成果を示しながらチームや会社に貢献
実例4:コミュニケーション・調整志向
- 強み:人をまとめる力・調整力
- 価値観:仲間と協力して成果を出すこと
- 求められること:プロジェクトマネジメントやイベント運営の需要
- 具体例:イベント運営会社でプロジェクトリーダーとしてチームをまとめ、円滑な進行と高い評価を得る
自己理解と市場理解を統合し、具体的な職務や役割に落とし込むことで、自分らしい働き方を描けます。
迷いを減らし、日々の意思決定に自信を持つための最も実践的な方法です。
第8章:まとめ|“迷わない自分”をつくるために
キャリア迷子を脱し、迷わない自分をつくるには、自己分析を一度きりの作業で終わらせず、定期的に見直す習慣を持つことが重要です。
キャリアは時間とともに変化します。
環境や価値観の変化に応じて、自分の強みや軸を確認・調整することで、どんな状況でもブレずに意思決定できます。
自己理解をメンテナンスすることで、迷いを最小化し、安心感を持ちながらキャリアを歩むことができるのです。
例えば、日記やマインドマップで定期的に振り返りを行ったり、コーチングで他者の視点を取り入れることが有効です。
過去の経験・強み・価値観を言語化し、未来の目標と照らし合わせることで、自分の軸が明確になり、変化しても迷わず行動できます。
実際に、毎月キャリアノートを更新している人は、判断に迷う場面でも自信を持って決断できるという報告があります。
自己分析は終わりのない旅です。
定期的な振り返りと軸の確認を習慣化することで、変化の中でも自分らしい選択が可能になります。
まずは、あなたのキャリアノートを開き、過去の経験や価値観を書き出すことから始めましょう。
小さな一歩が、迷わない自分をつくる大きな一歩になります。
