-
【保存版】なぜ自信が仕事を変えるのか?できる人の共通習慣
 第1章|なぜ「自信」が仕事の結果を左右するのか 「自信がある人」と聞くと、堂々としていて、強くて、失敗しなさそうな人を思い浮かべるかもしれません。 でも、実際に仕事で成果を出している人たちを見ていると、必ずしも“最初から自信満々だった人”ばかりではありません。 むしろ多いのは、不安や迷いを抱えながらも、それでも前に進める人です。 仕事の場面では、 提案する 判断する 人前で話す 責任を引き受ける こうした行動が求められます。ここで自信がないと、行動が一歩遅れたり、言葉が弱くなったりし...
第1章|なぜ「自信」が仕事の結果を左右するのか 「自信がある人」と聞くと、堂々としていて、強くて、失敗しなさそうな人を思い浮かべるかもしれません。 でも、実際に仕事で成果を出している人たちを見ていると、必ずしも“最初から自信満々だった人”ばかりではありません。 むしろ多いのは、不安や迷いを抱えながらも、それでも前に進める人です。 仕事の場面では、 提案する 判断する 人前で話す 責任を引き受ける こうした行動が求められます。ここで自信がないと、行動が一歩遅れたり、言葉が弱くなったりし... -
【保存版】忙しくてもできる学びながら稼ぐ副業の始め方
 第1章|「副業したいけど、時間がない」その悩みは、あなただけじゃない 「副業に興味はある。でも、正直そんな時間はない」この言葉、何度も心の中でつぶやいたことがある人は多いはずです。 仕事が終わればクタクタ。家に帰れば家事や育児。やっと一息ついた頃には、もう寝る時間。 SNSを開くと、「副業で月10万円」「スキマ時間で収入アップ」そんな言葉が並んでいて、焦る気持ちだけが積み重なっていく。 でも、ここで一度立ち止まって考えてみてほしいんです。 副業って、本当に“時間がある人だけのもの”でし...
第1章|「副業したいけど、時間がない」その悩みは、あなただけじゃない 「副業に興味はある。でも、正直そんな時間はない」この言葉、何度も心の中でつぶやいたことがある人は多いはずです。 仕事が終わればクタクタ。家に帰れば家事や育児。やっと一息ついた頃には、もう寝る時間。 SNSを開くと、「副業で月10万円」「スキマ時間で収入アップ」そんな言葉が並んでいて、焦る気持ちだけが積み重なっていく。 でも、ここで一度立ち止まって考えてみてほしいんです。 副業って、本当に“時間がある人だけのもの”でし... -
【保存版】選ばれ続ける人になるためのキャリア戦略と成長習慣
 第1章|なぜ今、「キャリア戦略」が必要なのか 「今の仕事、このままでいいんだろうか」忙しい日々の中で、ふとそんな疑問が頭をよぎったことはありませんか。 かつては、会社に入れば定年まで勤め上げることが“当たり前”とされていました。しかし今はどうでしょう。終身雇用は揺らぎ、AIやテクノロジーの進化によって仕事の形は日々変化し、副業や転職、フリーランスという選択肢も一般的になりました。 この時代に求められているのは、「がんばること」よりも「考えて選ぶこと」。つまり、自分のキャリアを“戦略...
第1章|なぜ今、「キャリア戦略」が必要なのか 「今の仕事、このままでいいんだろうか」忙しい日々の中で、ふとそんな疑問が頭をよぎったことはありませんか。 かつては、会社に入れば定年まで勤め上げることが“当たり前”とされていました。しかし今はどうでしょう。終身雇用は揺らぎ、AIやテクノロジーの進化によって仕事の形は日々変化し、副業や転職、フリーランスという選択肢も一般的になりました。 この時代に求められているのは、「がんばること」よりも「考えて選ぶこと」。つまり、自分のキャリアを“戦略... -
【保存版】頑張らなくても仕事が回り出すミニマル習慣のつくり方
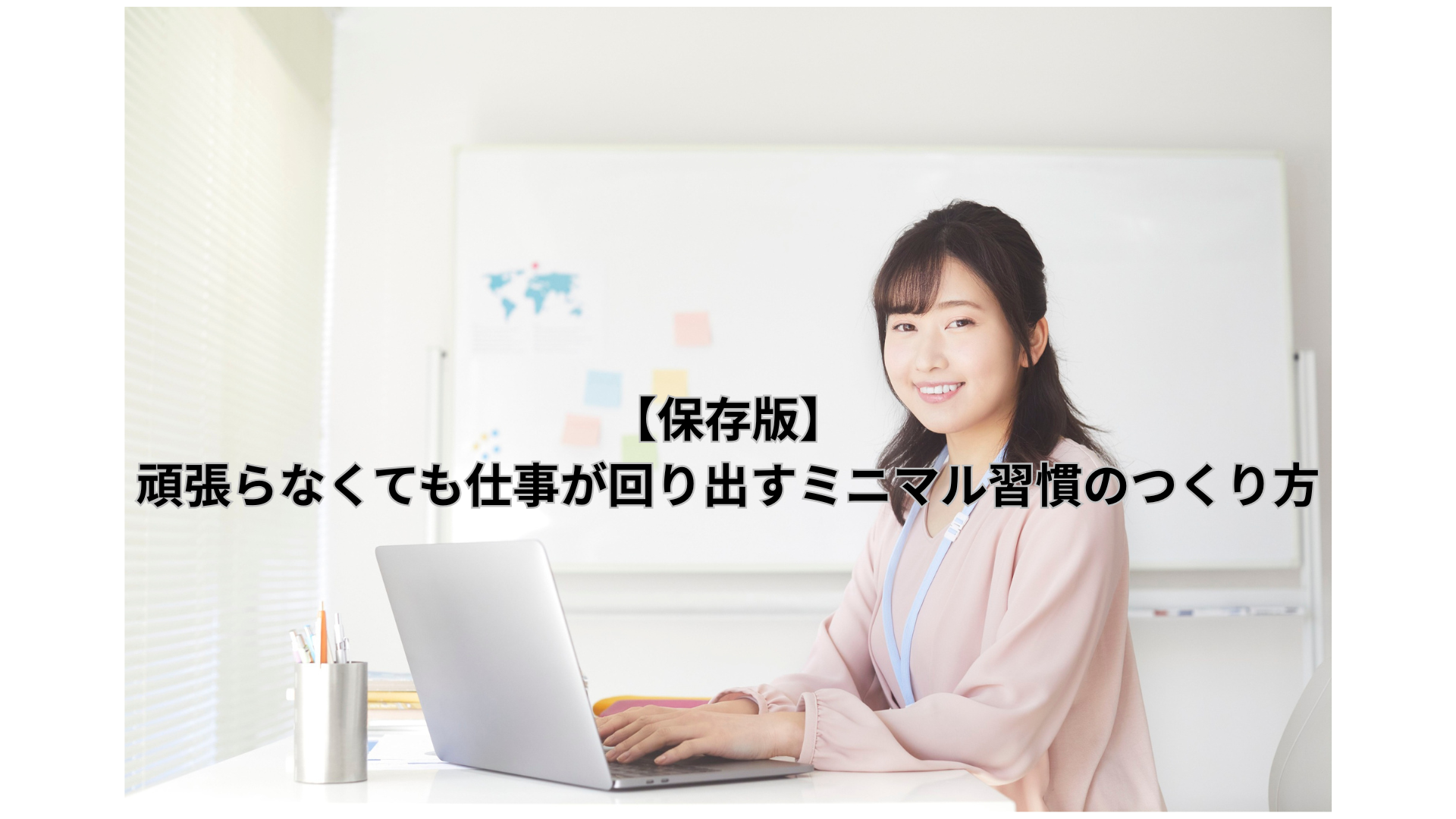 第1章|なぜ、私たちは「やる気」に頼るほど疲れていくのか 「今年こそは習慣化するぞ」「今度こそ三日坊主は卒業したい」 そう思って手帳を買い、アプリを入れ、気合い十分でスタートしたのに、気づけばフェードアウト。そんな経験、きっと一度や二度じゃないはずです。 ビジネスの現場でも同じです。・毎朝早起きして勉強しよう・仕事後に副業の時間を確保しよう・部下とのコミュニケーションを意識しよう どれも正しい。どれも必要。でも、続かない。 ここで多くの人はこう考えます。「自分は意志が弱い」「も...
第1章|なぜ、私たちは「やる気」に頼るほど疲れていくのか 「今年こそは習慣化するぞ」「今度こそ三日坊主は卒業したい」 そう思って手帳を買い、アプリを入れ、気合い十分でスタートしたのに、気づけばフェードアウト。そんな経験、きっと一度や二度じゃないはずです。 ビジネスの現場でも同じです。・毎朝早起きして勉強しよう・仕事後に副業の時間を確保しよう・部下とのコミュニケーションを意識しよう どれも正しい。どれも必要。でも、続かない。 ここで多くの人はこう考えます。「自分は意志が弱い」「も... -
【保存版】忙しくても続く、自己成長のためのシンプル日記習慣
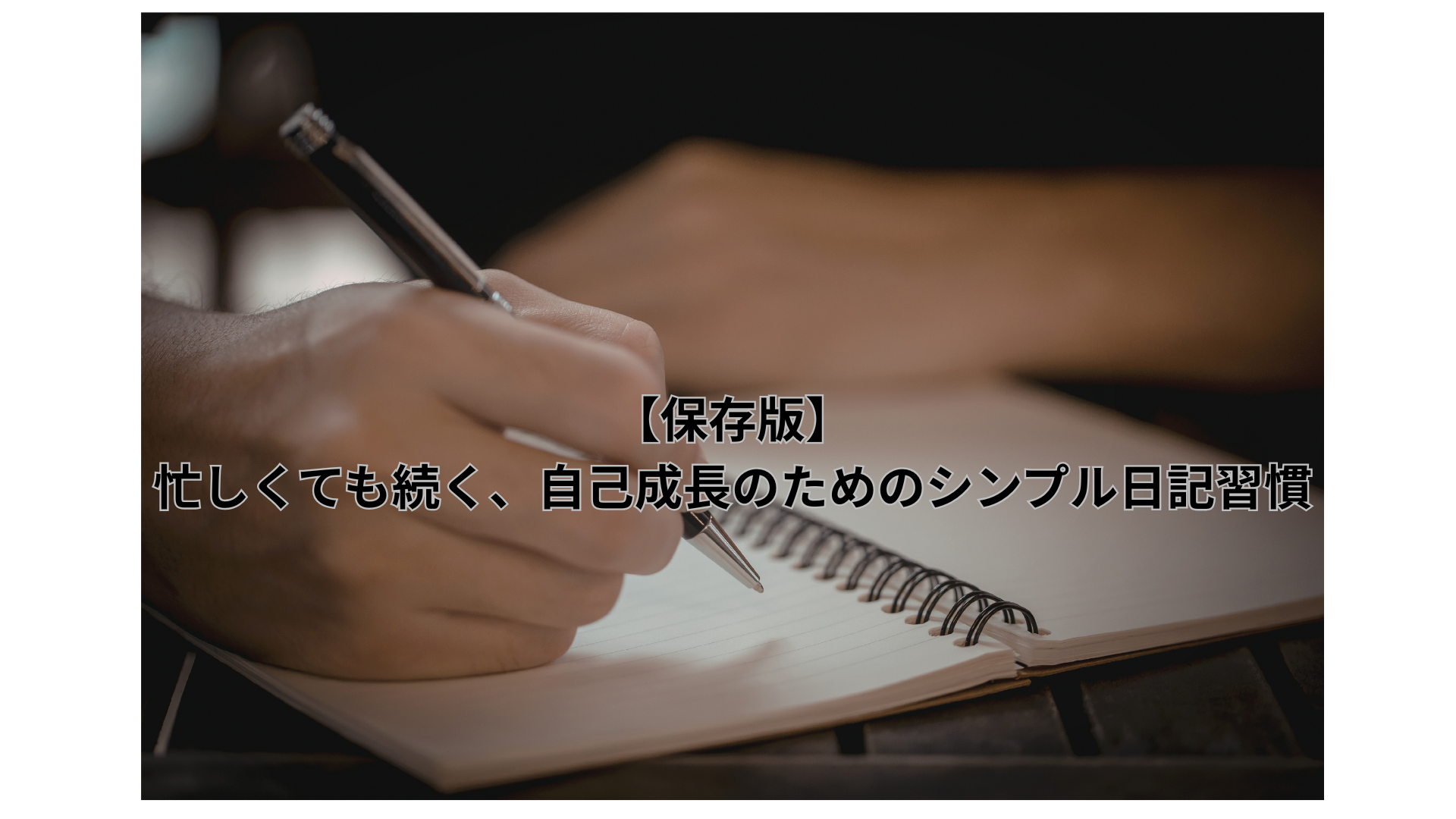 第1章 三日坊主は「意志が弱い」のではない 「また続かなかった……」 自己啓発本を読み終えた直後や、新しい習慣を始めて数日後、そんな言葉を心の中でつぶやいたことはありませんか? 早起き、勉強、運動、日記、振り返り。ビジネスに役立つと分かっているのに、なぜか続かない。 多くの人は、ここで自分を責めます。「自分は意志が弱い」「やっぱり向いていない」「忙しいから仕方ない」 でも、はっきり言います。三日坊主は、性格の問題ではありません。 原因はもっとシンプルで、そしてほとんどの人が“同じと...
第1章 三日坊主は「意志が弱い」のではない 「また続かなかった……」 自己啓発本を読み終えた直後や、新しい習慣を始めて数日後、そんな言葉を心の中でつぶやいたことはありませんか? 早起き、勉強、運動、日記、振り返り。ビジネスに役立つと分かっているのに、なぜか続かない。 多くの人は、ここで自分を責めます。「自分は意志が弱い」「やっぱり向いていない」「忙しいから仕方ない」 でも、はっきり言います。三日坊主は、性格の問題ではありません。 原因はもっとシンプルで、そしてほとんどの人が“同じと... -
【保存版】なぜ伸び続ける人はお金にも困らなくなるのか?
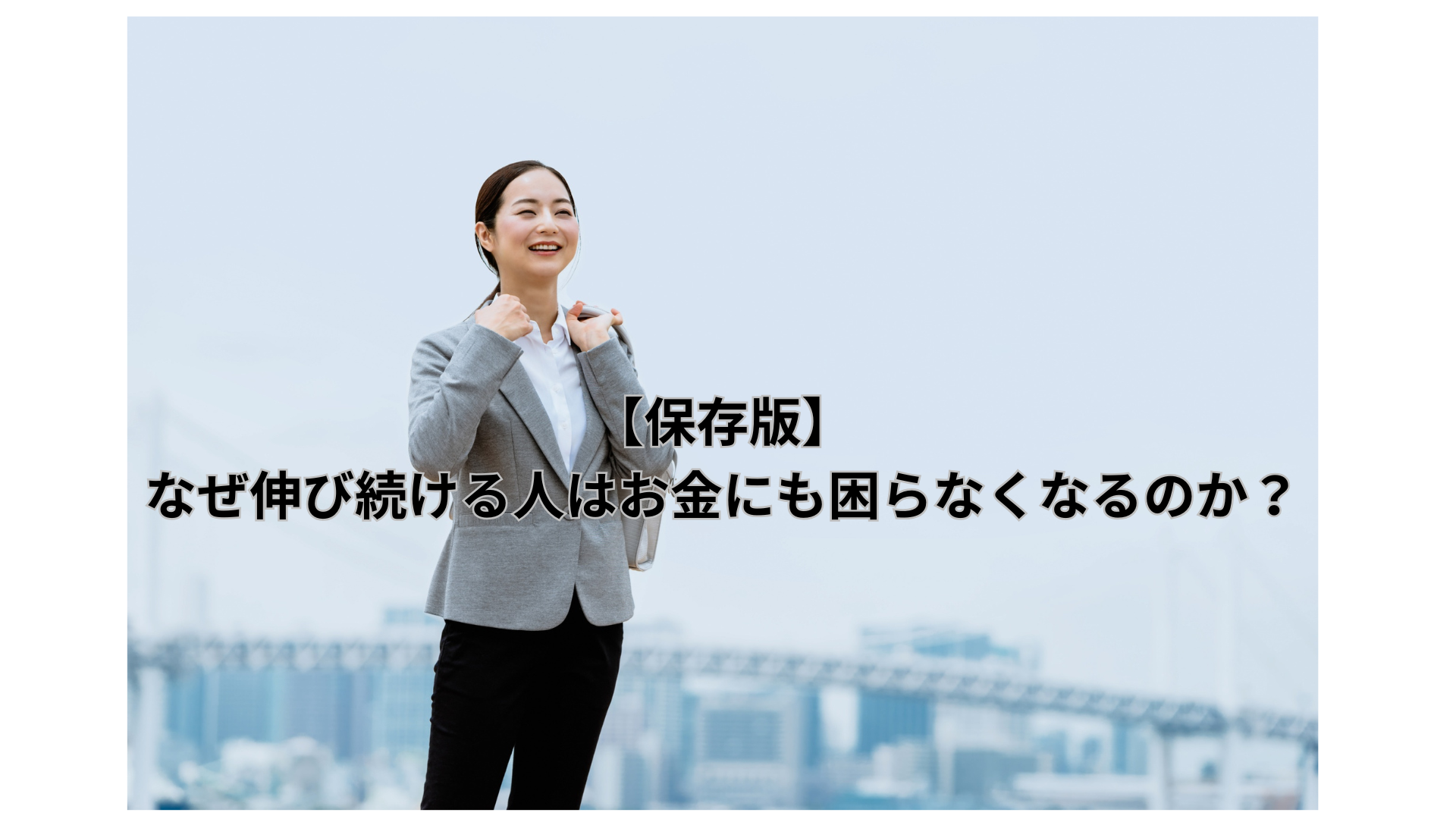 第1章|「富」を追いかけるほど、なぜ遠ざかるのか 「もっと稼ぎたい」「収入を増やしたい」ビジネスに関わっていると、そんな気持ちを抱くのはとても自然なことです。 私自身も、かつては「どうすれば早く結果が出るのか」「効率よく儲かる方法は何か」そんな問いばかりを頭の中で転がしていました。 でも、ある時ふと気づいたのです。“富”を直接追いかけているうちは、なぜか手応えが薄いということに。 一時的に収入が増えても、不安は消えない。新しい案件を取っても、次が見えない。どこか常に「追われている...
第1章|「富」を追いかけるほど、なぜ遠ざかるのか 「もっと稼ぎたい」「収入を増やしたい」ビジネスに関わっていると、そんな気持ちを抱くのはとても自然なことです。 私自身も、かつては「どうすれば早く結果が出るのか」「効率よく儲かる方法は何か」そんな問いばかりを頭の中で転がしていました。 でも、ある時ふと気づいたのです。“富”を直接追いかけているうちは、なぜか手応えが薄いということに。 一時的に収入が増えても、不安は消えない。新しい案件を取っても、次が見えない。どこか常に「追われている... -
【保存版】なぜあの人は好かれるのか?仕事が楽になる思考習慣
 第1章|なぜ「好かれる人」はビジネスで強いのか 仕事ができる人が、必ずしも「好かれる人」とは限らない。でも、好かれている人は、結果的に仕事がうまくいっていることが多い。 ・相談されやすい・情報が自然と集まる・多少の失敗が許される・チャンスを先に回してもらえる こうした“見えないアドバンテージ”は、実は能力差ではありません。人との関係性の中で、少しずつ積み上がった信頼の総量です。 好かれる人たちをよく観察すると、✔ 無理に愛想を振りまいているわけでもない✔ 話術が特別うまいわけでもない...
第1章|なぜ「好かれる人」はビジネスで強いのか 仕事ができる人が、必ずしも「好かれる人」とは限らない。でも、好かれている人は、結果的に仕事がうまくいっていることが多い。 ・相談されやすい・情報が自然と集まる・多少の失敗が許される・チャンスを先に回してもらえる こうした“見えないアドバンテージ”は、実は能力差ではありません。人との関係性の中で、少しずつ積み上がった信頼の総量です。 好かれる人たちをよく観察すると、✔ 無理に愛想を振りまいているわけでもない✔ 話術が特別うまいわけでもない... -
【保存版】仕事で自信を失う人の共通点?無意識にやっている脳のクセ
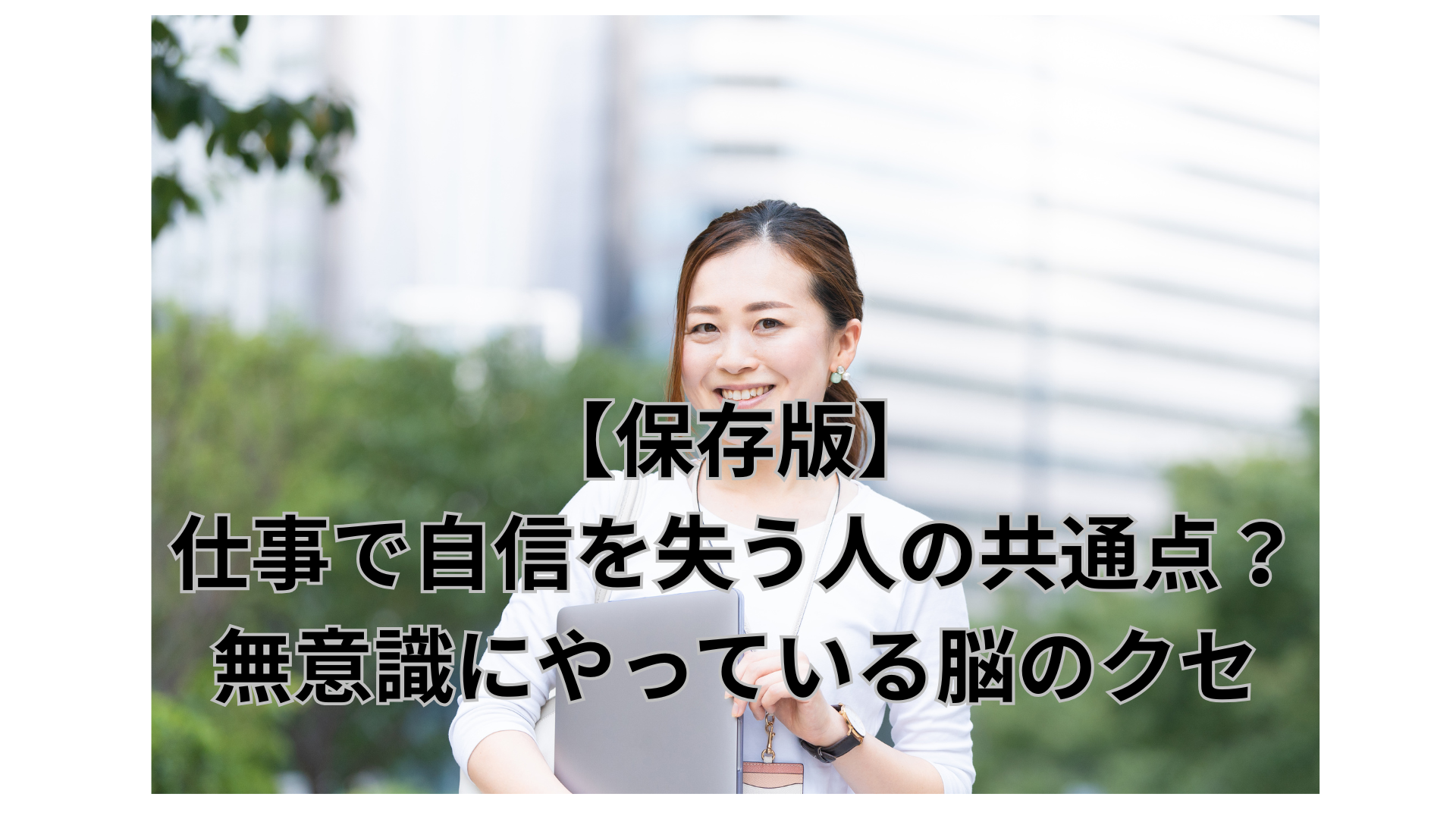 第1章|「自信がない」は、あなたの性格じゃない 「なんで私は、こんなに自信がないんだろう」 仕事で成果を出しても、誰かに褒められても、次の瞬間には「でもたまたまだよね」「私なんてまだまだ」と思ってしまう。 そんな自分に、うんざりしたことはありませんか。 でもね、最初に伝えたいことがあります。自信がないのは、あなたの性格でも、能力不足でもありません。 それはただ、“脳の使い方のクセ”なだけ。 ビジネスの現場で「自信がある人」「堂々としている人」を見て、「メンタルが強いんだろうな」と思...
第1章|「自信がない」は、あなたの性格じゃない 「なんで私は、こんなに自信がないんだろう」 仕事で成果を出しても、誰かに褒められても、次の瞬間には「でもたまたまだよね」「私なんてまだまだ」と思ってしまう。 そんな自分に、うんざりしたことはありませんか。 でもね、最初に伝えたいことがあります。自信がないのは、あなたの性格でも、能力不足でもありません。 それはただ、“脳の使い方のクセ”なだけ。 ビジネスの現場で「自信がある人」「堂々としている人」を見て、「メンタルが強いんだろうな」と思... -
【保存版】不安なままでいい。伸びる人になる副業習慣
 「副業したほうがいいのは分かってる」「このまま今の働き方だけでいいのかな、って不安になる」 そんな気持ち、きっと一度は感じたことがありますよね。でも同時に、「何から始めたらいいか分からない」「自分にできることなんてあるのかな」そんな迷いも一緒についてきませんか。 実は、副業で伸びる人と伸びない人の差は、才能でもスキルでもありません。もっと手前の、「考え方」と「向き合い方」にあります。 この記事では、・これから副業を始めたい人・始めたけれど、なかなか成果が出ない人・忙しい中でも...
「副業したほうがいいのは分かってる」「このまま今の働き方だけでいいのかな、って不安になる」 そんな気持ち、きっと一度は感じたことがありますよね。でも同時に、「何から始めたらいいか分からない」「自分にできることなんてあるのかな」そんな迷いも一緒についてきませんか。 実は、副業で伸びる人と伸びない人の差は、才能でもスキルでもありません。もっと手前の、「考え方」と「向き合い方」にあります。 この記事では、・これから副業を始めたい人・始めたけれど、なかなか成果が出ない人・忙しい中でも... -
【保存版】迷いながら成長する人のためのセルフアップ戦略
 第1章|なぜ今、「セルフアップ」が働き方を左右するのか 「このままの働き方で、あと5年後も大丈夫だろうか?」 忙しい日々の中で、ふとそんな不安がよぎる瞬間はありませんか。仕事はこなしている。大きなミスもしていない。それなのに、どこか成長実感が薄く、未来がぼんやりして見える。 これまでの時代は、「会社が成長の道筋を用意してくれる」ことが当たり前でした。スキルアップの研修があり、昇進のレールがあり、頑張ればそれなりに評価される。 でも今は違います。 ・環境の変化が早すぎる・正解が一つ...
第1章|なぜ今、「セルフアップ」が働き方を左右するのか 「このままの働き方で、あと5年後も大丈夫だろうか?」 忙しい日々の中で、ふとそんな不安がよぎる瞬間はありませんか。仕事はこなしている。大きなミスもしていない。それなのに、どこか成長実感が薄く、未来がぼんやりして見える。 これまでの時代は、「会社が成長の道筋を用意してくれる」ことが当たり前でした。スキルアップの研修があり、昇進のレールがあり、頑張ればそれなりに評価される。 でも今は違います。 ・環境の変化が早すぎる・正解が一つ...